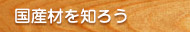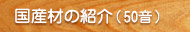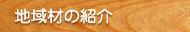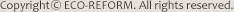建材としても需要が増している国産材の乾燥について。

住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任が法律で義務付けられたこともあり、製材業界では国産材の乾燥について注目する動きが高まっています。
木材の乾燥収縮に伴う狂いや曲がり、割れなどは、クロスの亀裂や床鳴り、建具の開閉の不具合等を招きかねません。そのため、寸法安定性の高い乾燥材や集成材の需要が高まっているのです。
乾燥材とは乾燥処理を施した木材のことで、処理方法は大きく分けて、天然乾燥と人工乾燥があります。
天然乾燥では、屋外に木材を積み重ねておき、太陽光と自然の風で木材を乾燥させます。
一方人工乾燥では、温度や湿度、風の流れなどを操作して木材を乾燥させます。乾燥度は含水率として表されます。
国産材を乾燥させるメリットとしては、建材として使用された後の不具合を防げること、木材の変色や腐れを防げること、強度性能が増すこと、塗装性・加工性・接着性が高まることなどが挙げられます。
国産材の乾燥について「葉枯らし」という言葉を目にすることがありますが、これは伐採した丸太に葉をつけたまま、その場で40~50日放置し、葉から水分を蒸発させる方法です。
葉枯らしにより、木材の色を良くし、軽量になって集材や運搬が容易になるなどのメリットがありますが、含水率の低下はあまり期待できません。